artscapeレビュー
2014年07月15日号のレビュー/プレビュー
村田兼一「少女観音」

会期:2014/05/30~2014/06/15
神保町画廊[東京都]
村田兼一はやはりただ者ではない。1990年代以来、彼は自宅でもある大阪市郊外の旧家をスタジオに改装し、女性モデルたちとともに耽美的なヌード・フォトを制作し続けてきた。これだけ長く続けていると、手法や発想が固定化して、マンネリに陥りがちになる。ところが、村田はその危機を巧みに回避しつつ、あの手この手で新たなシリーズを作り続けてきた。今回の「少女観音」のシリーズも、いかにも村田らしい遊び心にあふれる作品に仕上がっている。
聖なる存在にエロス的な感情を注いで崇拝することは、古今東西広く行なわれてきた。キリスト教の世界では、聖マリアがその役目を果たすことが多い。日本でも女身の姿をとる観音仏がエロスの受け皿になってきた。村田はそのような伝統的な枠組を逆手にとり、「少女観音」というトリッキーな仕掛けを編み出した。恐るべき淫らなポーズをとる少女たちを仏像に見立てることで、ちょっと困ってしまうほどに目覚ましく、魅力的な視覚的エンターテインメントが成立している。
このシリーズ、まだ発展していく余地がありそうだ。安倍文殊院の文殊菩薩と善財童子の姿かたちをそのまま借用した作品もあるが、多くはそれらしい思いつきのポーズで写されている。もう少し厳密に仏像のイコノロジーを適用した方がいいかもしれない。また、フレーミングや会場のレイアウトも、もっと凝ってもよさそうだ。また掛け軸、金屏風、装飾的なフレームなどを効果的に使い、和風のテイストを強調することで、よりキッチュでアイロニックな雰囲気が強まるのではないだろうか。
2014/06/01(日)(飯沢耕太郎)
映画をめぐる美術──マルセル・ブロータースから始める

会期:2014/04/22~2014/06/01
東京国立近代美術館 企画展ギャラリー[東京都]
国立近代美術館の「映画をめぐる美術──マルセル・ブロータースから始める」展を見る。以前、同館で開催された「ヴィデオを待ちながら」展が、1960年代から新しい表現手段として登場したヴィデオ・アートの基本的な作品を一同に集めた入門編だとすれば、今回はマルセル・ブロータースの試みを共通の入り口にして、6つのテーマにもとづき、個別の部屋に誘い、他の作家を紹介するというハイブロウな内容だった。アメリカの銀行強盗事件を再現するピエール・ユイグや、音声が失われた母の過去の映像を調査するアンリ・サラの作品が興味深い。同館の展示によく関わる、建築家の西澤徹夫による会場構成も秀逸である。
2014/06/01(日)(五十嵐太郎)
門井幸子「春 その春」

会期:2014/05/26~2014/06/08
ギャラリー蒼穹舍[東京都]
門井幸子のような写真家の作品について、うまく伝えるのはむずかしい。被写体になっているのは、ありふれているとしかいいようのない風景であり、撮影の仕方にも特に構えた所はない。それらを隅々までしっかりと気を配ったモノクロームプリントに丁寧に焼き付けて展示する。だが、今回東京・新宿のギャラリー蒼穹舍で展示された「春 その春」のシリーズを見ると、その「何でもない」写真たちが、じわじわと不思議な力で食い込んでくるような気がする。その理由を説明するのがなかなかむずかしいのだ。
彼女の写真集『KADOI SACHIKO PHOTOGRAPHS 2003-2008』(蒼穹舍、2008年)のあとがきにあたる文章に、次のように記されているのを見つけて「なるほど」と思った。
「撮り終えたあともしばらくたたずみ、その風景を見つめながら、消え去ること、そして生き続けることを思う」
誰しも「風景」を前にして、生と死について深い思いに沈むことがあるのではないだろうか。実は写真家は撮ることに集中しているので、そのような沈思黙考の時を過ごすことはあまりない。だが門井の「何でもない」写真群は、それぞれ「撮り終えたあと」の放心と思い入れの時間をたっぷりと含み込んで成立しているように見える。そしてわれわれ観客もまた、2011~14年に北海道、根室半島の早春の時期を撮影した写真を目にした後で、「春 その春」という感慨とともに、緩やかに過ぎていくその時間の厚みを追体験することになるのである。
2014/06/03(火)(飯沢耕太郎)
幻の前衛写真家──大西茂展
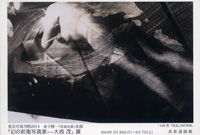
会期:2014/05/26~2014/06/07
表参道画廊[東京都]
本展は写真史家の金子隆一氏の企画で、「東京写真月間2014」の一環として開催された。大西茂(1928~94)の作品、20点がこのような形で公開されたのは初めてであり、「こんな写真家がいたのか!」という驚きを与えてくれる展示だった。この所、急速に進展している日本写真史の再構築に大きく寄与する展覧会といえるだろう。
岡山県出身の大西は北海道大学理学部で数学を学び、1953年に同大学卒業後も研究室に残って研究を続けた。一方で写真にも関心を持ち、55年になびす画廊で初個展を開催、56年の国際主観主義写真展にも出品する。57年には瀧口修造の企画によりタケミヤ画廊で第2回個展を開催する。同年『別冊アトリエ』や『フォト35』にも作品を発表するが、その後は墨象作家として活動するようになり、写真作品の発表は途絶してしまう。
大西の作風は、本展のタイトルにあるように、まさに1930年代に関西や名古屋で大きな盛り上がりを見せた「前衛写真」の衣鉢を継ぐものといえる。だが、シュルレアリスム的なコラージュやオブジェの構成を主流とする戦前の「前衛写真」とも微妙に違っていて、多重露光や現像液を刷毛のようなもので塗布する特殊な処理を多用する画面は、激しく、荒々しいエネルギーを発している。のちに、「アンフォルメル」を提唱したフランスの美術批評家、ミシェル・タピエが彼の墨象作品を高く評価したことでもわかるように、それらは写真という枠組から大きく逸脱していく要素を孕んでいたのだ。
この「遅れてきた(同時に「早過ぎた」)前衛写真家」の作品をどのように位置づけていくかは、今後の大きな課題だろう。また、1950年代という時代に、彼のような作家を生み出していく土壌があったことにも注目していかなければならない。「幻の」写真家は、大西の他にももっといそうな気がする。
2014/06/03(火)(飯沢耕太郎)
「新印象派──光と色のドラマ」記者発表会

会期:2014/06/04
東京都美術館講堂[東京都]
壇上には東京会場の都美術館の真室佳武館長と、大阪会場のあべのハルカス美術館の浅野秀剛館長が並んだが、キマジメにごあいさつをする真室館長に対し、浅野館長は展覧会そっちのけであべのハルカスとハルカス美術館の話ばかり。せっかく上京したんだから宣伝しとかなくちゃね。肝腎の展覧会については都美術館の学芸員から解説があったが、総監修も監修もフランスの美術史家が務めてるため、通り一遍の紹介。もちろんスーラの《アニエールの水浴》も《グランド・ジャット島の日曜日の午後》も来ないけど(後者の部分的習作は来る)、それでもスーラだけで計7点、ほかにシニャック、エドモン・クロス、ヤン・トーロップらの作品が見られるし、「科学との出会い──色彩理論と点描技法」に1章が費やされるのも楽しみ。最後に、ハルカス展望台のキャラクター「あべのべあ」と上野駅のキャラクター「エキュート上野パンダ」が仲よく登場。上野パンダはなんの芸もないただの白黒パンダだが、あべのべあは空色のクマの体に雲が漂うシュールな着ぐるみ。それぞれアカデミズムと新印象派を象徴してるんだろうか。
2014/06/04(水)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)