artscapeレビュー
2022年06月15日号のレビュー/プレビュー
Chim↑Pom展:ハッピースプリング

会期:2022/02/18~2022/05/29
森美術館[東京都]
結成から17年、日本を代表するアート・コレクティブとして名を馳せているChim↑Pom from Smappa!Group★の「最大の回顧展」が、森美術館で開催された。都市と公共性、ヒロシマ、東日本大震災、戦争、移民問題など多彩なテーマを扱い、メキシコとアメリカの国境地帯、カンボジアまでも足を伸ばして、挑発とユーモアがないまぜになったパフォーマンスを縦横無尽に展開し、それらを映像を含めた総合的な現代アートとして提示する彼らの活動が、まさにコレクティブに集成された見応えのある展示である。
それらを見ながら、あらためてプロジェクトにおけると写真・映像の役割について考えさせられた。いうまでもなく、アーティストたちのパフォーマンスは一回限りのものだから、その場にいた者以外の観客にそれを伝えるためには、写真や動画で記録しておく必要がある。逆にいえば、写真・映像こそが、その作品を成立させるために決定的な役割を果たすといえる。Chim↑Pom from Smappa!Groupはそのことをよく理解しており、展示されていた写真・映像のクオリティはとても高い。誰がそれらを撮影したのかは明記されていないが、たとえば彼らの活動を広く認知させた《ヒロシマの空をピカッとさせる》(2009)の写真・映像の強度はただならぬものがある。「May, 2020, Tokyo」(2020)では、「青写真の感光液を塗ったキャンバスを都内各所の大型看板に2週間にわたって設置」するという手法を用いて、まさに写真作品としかいいようのない大判プリントを制作・発表した。彼らの活動を写真家のそれとして捉え直すこともできるということだ。
ひるがえって、写真の分野でChim↑Pom from Smappa!Groupに匹敵する活動を展開している者がいるかといえば、Spew、二人、Culture Centreなどのユニットと、個人の制作作業とを両立させてきた横田大輔くらいしか思い浮かばない。写真家たちによるアート・コレクティブの動きが、もっと出てきてもいいのではないだろうか。
★──本展会期中の2022年4月27日にChim↑Pom はChim↑Pom from Smappa!Groupへ改名した。http://chimpom.jp/project/namechange.html
2022/04/14(木)(飯沢耕太郎)
鶴巻育子「幸せのアンチテーゼ」

会期:2022/04/05~2022/04/17
Jam Photo Gallery[東京都]
鶴巻育子は、自らが主宰する東京・目黒のJam Photo Galleryで、昨年4月の「夢」に続いて「幸せのアンチテーゼ」と題する写真展を開催した。そこに展示されているのは、「自身の心理状態を探るため」に撮影を続けているという日常スナップの写真群である。「夢」では、横位置の黒白写真という枠をあえて定めて出品作を選んでいたのだが、今回はカラー写真も、縦位置の写真も入ってきた。では、写真の幅が広がった分、表現のフォーカスも拡散したのかといえば、決してそんなことはない。特に人が写っていない風景写真に、張り詰めた緊張感を湛えているものが増えて、それらが柔らかに包み込むような雰囲気の写真とうまく釣り合って並んでいた。
鶴巻がADHD(多動性の発達障害)を抱えているということを、彼女が展覧会に寄せたコメントではじめて知った。周囲の音が異常に気になって、現実感の喪失や離人症につながることもあり、スナップ写真を撮影するという行為は、彼女にとって現実世界とのかかわりを保つという切実な意味を持つもののようだ。とはいえ、写真家たちには、そのような心理的な傾きを持っている者が多いので、あまり深刻に受けとる必要はないだろう。自分と現実世界との間に薄膜が張っているような感覚は、むしろ写真撮影に集中するためにプラスに働くこともあるのではないかと思う。
今回の展覧会は、たしかに前回よりも先に進んでいた。とはいえ、まだ完成形ではない。いまの仕事をうまく育てていけば、写真家としての次のステージが見えてくるのではないだろうか。あと1回、あるいは2回の展示を経ることで、鶴巻の写真の世界がよりくっきりと形をとってきそうな気がする。
関連レビュー
鶴巻育子「夢」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年06月01日号)
2022/04/15(金)(飯沢耕太郎)
森村泰昌:ワタシの迷宮劇場

会期:2022/03/12~2022/06/05
京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ[京都府]
まさに圧巻としか言いようのない展示だった。森村泰昌は1980年代から、美術作品の登場人物、ポップスター、女優、20世紀を彩る偉人、古今東西のアーティストなど、さまざまな人物に「変身」するパフォーマンスを、写真作品として発表し続けてきた。その写真を撮影するときには、衣装やメーキャップやポーズを決定後に、まずポラロイド写真で仕上がりを確認する。今回の「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」展に出品されたのは、これまで撮り溜められてきたそれらの写真である。
いわば、絵画作品の下絵にあたるポラロイド写真は、普通は事前のチェックが終われば用済みになってしまう。ところが、そうやって撮り続けられた823枚のポラロイド写真群は、森村の仕事の現場の記録という以上の凄みを持ち始めているように感じた。ポラロイドの撮影は一回では終わらないことも多い。何度も、ポーズや表情を変えつつ、シャッターを切り続ける。ある人物になりきる行為が、森村にとって宗教的な儀式にも似た切実かつ絶対的な希求であることが、それら大量の、めくるめくような写真の群れから伝わってきた。
それにしても、森村はなぜ、何のために膨大な労力と時間と費用を費やして「変身」の作業を続けているのか。併催されていた30分近い朗読劇、「声の劇場」を視聴して、おぼろげながらその答えを見出したような気がした。学生時代のメモを元に再構成したというその物語のなかで、森村の分身と思われる主人公は、「顔」によって自己の一部を「食われて」しまう。おそらくその物語は、彼自身の原体験の表出といえるだろう。無数の「顔」によって食い尽くされ、その果てに無に帰したいという倒錯した願望が、森村の何者かになりきるという無償の行為を支えているのではないだろうか。
2022/04/27(水)(飯沢耕太郎)
平間至 写真展 すべては、音楽のおかげ

会期:2022/04/02~2022/05/08
美術館「えき」KYOTO[京都府]
タイトルがよく示すように、平間至の写真は「音楽」と強い親和性を持っている。宮城県塩竈市で写真館を営む父親は、チェロの愛好家でもあり、彼自身も子供の頃からヴァイオリンを習っていた。小学生の頃に初めて聴いたオーケストラの生演奏に衝撃を受け、10代にはパンク・ロックに夢中になる。写真家として活動するようになっても、「音楽」はまさに彼自身の表現活動のベースとして働き続けてきた。平間が撮影するミュージシャンの写真が、ほかの写真家たちとは一味違った、いきいきとした輝き、グルーヴ感を発しているのはそのためだろう。彼はミュージシャンたちと「音楽」という場を共有し、ともに巻き込み、巻き込まれていくやりとりを自在に行なうことができる写真家なのだ。
だが、初の回顧展というべき美術館「えき」KYOTOでの展示を見て思ったのは、平間の写真にはまた別の側面があるということだった。展示の中心になっていたのは、1996年からスタートしたタワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」のキャンペーンに代表される、「音楽」にどっぷりと浸かった、躍動的でエネルギッシュな作品群である。だが、平間にはもうひとつ、身の回りの事物を静かに見つめ、写しとっていく写真の系譜がある。今回の写真展でいえば、2011年の東日本大震災で実家のある東北の沿岸部が大きな被害を受けた後に、心身ともに消耗して、1年ほど自宅療養せざるを得なかった時期に撮影したという「光景」のパートがそうである。むしろ沈黙の声を聴き、それでもなお世界と自分とをカメラによってつなぎとめようと希求するようなそれらの写真群に、平間のもう一つの顔が覗いているのではないだろうか。動と静、その二つの要素が合わさったところに、写真家・平間至の写真世界の全体像が姿を現わすのではないかとも感じた。
2022/04/27(水)(飯沢耕太郎)
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2022
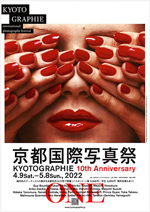
会期:2022/04/09~2022/05/08
京都府京都文化博物館 別館ほか[京都府]
このところ、コロナ禍もあって秋に会期を移していた「京都国際写真祭」が、ようやく通常通り4~5月に開催された。今回で10回目ということだが、前回からあまり間がなかったということもあり、華やかな印象はあまりなく、小さくまとまったイベントになった。
ギイ・ブルダン「The Absurd and The Sublime」(京都府文化博物館別館)、イサベル・ムニョス×田中泯×山口源兵衛「BORN-ACT-EXIST」(誉田屋源兵衛 黒蔵・奥座敷)、アーヴィング・ペン「Irving Penn: Works 1939-2007. Masterpieces from the MEP Collection」(京都市美術館別館)、奈良原一高「ジャパネスク〈禅〉」(両足院[建仁寺山内])など、それぞれしっかりと組み上げられた、クオリティの高い展示だったが、新たな展開が見えるというわけではない。
唯一、意欲的かつ刺激的なラインナップだったのは、細倉真弓、地蔵ゆかり、鈴木麻弓、岩根愛、殿村任香、𠮷田多麻希、稲岡亜里子、林典子、岡部桃、清水はるみが出品した「10/10 現代日本女性写真家達の祝祭」(HOSOO GALLERY)である。女性写真家たちを顕彰する「ウーマン・イン・モーション」プログラムの支援を受け、京都国際写真祭の共同創設者のルシール・レイボーズと仲西祐介、そして写真史家でインディペンデント・キュレーターのポリーヌ・ベルマールがキュレーションしたグループ展で、写真家たちの創作意欲を的確なインスタレーションに落とし込んだ充実した内容だった。
ただ、出品作家の表現の方向性があまりにもバラバラであり、なぜ、いま「現代日本女性写真家」という括りで写真展を企画するのかという意味づけも明確とはいえない。「複数の形態を持つ強く官能的な感情」を表出する殿村仁香「焦がれ死に die of love」と、父の死をきっかけに彼の故郷の村の祭事を撮影した地蔵ゆかり「ZAIDO」とを同居させるのは、やや無理があるのではないだろうか。とはいえ、東北の桜と伝統芸能とを撮影して震災とコロナ禍を結びつけようとする岩根愛の「A NEW RIVER」、北朝鮮に渡った日本人妻を丁寧に取材した林典子「sawasawato」の切迫感のあるインスタレーション、また、𠮷田多麻希、稲岡亜里子、清水はるみによる、これまで目にしたことがなかった新鮮なアプローチの作品を見ることができたのはとてもよかった。
「京都国際写真祭」も10回目ということで、ひとつの区切りを迎えつつある。いつも思うことだが、人選、会場、統一テーマ(今回は「ONE」)にあまり必然性が感じられないことなどを含めて、どのようなイベントにしていくのかを、もう一度再考すべき時期がきているのではないだろうか。
2022/04/29(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)