artscapeレビュー
あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術
2016年10月15日号
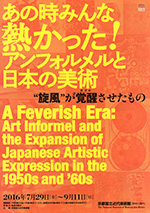
会期:2016/07/29~2016/09/11
京都国立近代美術館[京都府]
1950年代初頭、欧米で同時多発的に登場した熱く激しい抽象表現美術に対して、「アンフォルメル」(未定形なるもの)と名付けたフランス人美術評論家、ミシェル・タピエ。この動向は、展覧会やタピエの評論の翻訳を通じて50年代後半に日本に紹介され、特に56年に開催された「世界・今日の美術展」は大反響を呼び、「アンフォルメル旋風」を引き起こした。57年にはタピエが来日し、「世界・現代芸術展」を企画。デュビュッフェ、デ・クーニング、フォートリエ、フォンタナ、マチュー、ポロックなど自身が推す欧米作家に加えて、吉原治良、白髪一雄、嶋本昭三、田中敦子ら具体美術協会の作家や勅使河原蒼風、福島秀子、今井俊満、堂本尚郎といった日本人作家を組み入れて展示した。美術ジャーナリズム上では58年に終息する「旋風」だが、本展は、その影響力の射程を60年代前半まで広げ、約100点の作品を通して考察している。
本展の構成は、タピエが推した欧米作家12人の作品を展示した第1章と、「身体・アクション」「原始・生命」「反復・集合」「マチエール・物質」といったキーワードから日本での受容と展開を考察する第2~5章からなる。本展のポイントは、1)油彩画だけでなく、日本画、染織、陶芸、生け花といったジャンル横断的な影響の検証、2)爆発的な流行を受け入れた下地として、各キーワード毎に、「前衛書道との親和性」、「岡本太郎による縄文土器の『発見』(1951)や『メキシコ美術展』(東京国立博物館、1955)の反響に見られる、原始的な生命力への希求」、「日本画の画面構造の非中心性や平板な空間」、「物質の素材感に対する日本人独自の感受性」を挙げ、複数の要因を指摘している点である。
ここで問題提起をしているのは、2)の指摘である。タピエの言説と展覧会企画によって強力に推進された「アンフォルメル」が、「熱い」抽象表現をめぐる戦後の美術の主導権争いであった以上、ここには、「(欧米発信・主導の)国際的な美術動向の受容とローカリティ」という問題が横たわっている。確かに、森田子龍や井上有一らの前衛書家と、戦後の抽象絵画の方向性を模索する美術家との交流は、50年代初頭からあった。また、本展の展示の見どころの一つに、16mの長さに及ぶ篠原有司男の《ボクシング・ペインティング》と前衛書道の並置がある。墨を全身全霊で叩きつけた篠原の作品と並置されることで、前衛書道における生々しい身体性やエネルギーの過剰さが浮上し、紙面からはみ出した太い線は、漢字としての意味を失って抽象化へと接近している。しかし、ここで注意したいのは、「書道」も、「縄文土器やメキシコ美術」も、「日本画」も、還元すれば「非西欧、前近代」のモメントへと折り返されるということだ。それは対内的には、「起源」を反復するトートロジーであり、「伝統や土着の文化との親和性・連続性」を担保することで受容を推進する一方、対外的にはエキゾティシズムを発動させ、商品として差異化する記号として働くだろう。美術の国際的な基準への参入に際して、対内的にも対外的にも、ローカリティが価値づけを保証するものとして積極的に召喚される、という構造的な問題がここに露呈している。
また、第5章「マチエール・物質」も複数の問題をはらむ。この最終章では、アンフォルメルの影響力の射程を「旋風」終了の58年を区切りとして切断するのではなく、60年代前半まで射程圏に収め、絵具の物質性を強調したスタイルから、石、砂、麻袋、木片、陶片、アスファルトなどの「物質」を貼り込んだ絵画を紹介している。さらに、57年結成の「九州派」や荒川修作、工藤哲巳、高松次郎など、「読売アンデパンダン展」を中心に展開した「反芸術」も連続性のうちに捉えている。ここでの疑問は3点挙げられる。1)「農耕民族としての土との親和性や、素材感への感受性」をアンフォルメル受容の一要因と見なす姿勢に対する疑問。「超時代的な民族性」といったものが、はたして自明な存在としてあるのか? 2)素材が喚起する、脱ニュートラルな意味性。例えば、九州派がよく用いた「アスファルト」や「麻袋」という素材は、単に物質性の強調という審美的な側面を超え、近代化・工業化と労働、さらには炭鉱と労働争議、左翼的な政治性といった同時代の社会性への示唆を含む。こうした素材の使用は、その触覚性と脱ニュートラルな意味性において、「視覚性だけで完結する」とするモダニズム美学への批評として考えられるべきではないか。3)「絵具の物質性の強調」から「生の物質そのものの露呈」がはらむ射程の範囲について。この最終章では、絡まり合った紐を貼り付け、画面を黒い円形に塗った高松次郎の《点(No.16)》(1961-62)も含むことから、概念芸術への射程も示唆されている。では、高松を経由して、行きつく先は「もの派」まで射程圏を広げることはできるのか? この問いへの答えは提示されないまま宙吊りに終わっていた点が惜しまれる。
2016/09/03(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)