artscapeレビュー
2020年08月01日号のレビュー/プレビュー
荒木経惟『荒木経惟、写真に生きる。』

発行所:青幻舎
発行日:2020年5月25日
荒木経惟は今年80歳(傘寿)を迎えた。それを記念して、誕生日の5月25日に刊行されたのが本書『荒木経惟、写真に生きる。』である。三部構成で、撮り下ろしの写真作品「傘寿いとし」(31点)、樹木希林、中村勘三郎、荒木陽子、桑原甲子雄、森山大道、ビートたけし、ロバート・フランク、草間彌生らとの出会いとかかわりを語った「荒木経惟 写真に生きる 写真人生の出会い」、そして誕生(1940)から現在(2020)までの詳細な年譜「ドキュメンツ 荒木経惟」がその内容である。
このところ、あまり体調がよいとはいえず、コロナ自粛期間に外出を控えたこともあり、「傘寿いとし」の写真はすべてマンションの自室とバルコニーで撮られている。花々とビザールなフィギュアや人形などとの組み合わせは、これまで何度も手掛けてきたものであり、それ自体に新鮮味はない。だが中に何点か、ざわざわと心が揺れ騒ぐような写真が含まれていた。白い手袋と老人の小さな面をあしらった作品、すでに荒廃の気配が漂い始めたバルコニーの一隅を撮影した写真などだが、そのぶっきらぼうに投げ出したような表現のあり方に、逆に凄みを感じる。「傘寿」の祝祭的な気分を吹き飛ばすような写真にこそ、荒木の真骨頂があらわれているのではないだろうか。
第二部の自伝的な語り下ろしは、これまで発表されてきたインタビューやエッセイとかぶるものが多い。むしろ、内田真由美が編集・執筆した第三部の年譜が大事になってきそうだ。荒木のような多面的な活動を展開してきた写真家の場合、その広がりを万遍なく押さえるだけでも大変な手間がかかる。今回の年譜はそれだけでなく、荒木の写真世界の成り立ちと展開にしっかりと目配りしており、今後の荒木論のための、最も重要な基礎資料のひとつとなっていくだろう。
関連レビュー
荒木経惟「私、写真。」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年03月15日号)
荒木経惟 写狂老人A|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年08月01日号)
2020/07/22(水)(飯沢耕太郎)
中川馬骨『虚の胞衣』

発行所:東京綜合写真専門学校出版局
発行日:2020年6月26日
1977年、茨城県生まれの中川馬骨(なかがわ・まこつ)は、2001年に慶應義塾大学文学部哲学科卒業後、東京綜合写真専門学校で学び、2005年に同校写真芸術第二学科を卒業した。いくつかの公募展に出品しているが、本書が最初の本格的な写真集となる。
中川は父が50歳のときに生まれた。そのため、幼い頃から近い将来の父親の死を予感しながら育ってきたという。東京綜合写真専門学校在学中から、8×10インチ判の大判カメラで、折に触れて父を撮影し始めたのも、その不安をなんとか鎮めようという思いがあったからだった。2013年に父が亡くなったとき、覚悟はしていたものの衝撃は大きく、茫然自失の日々を過ごす。4年後の2017年にようやく決意してその遺骨を取り始める。そのことで、生前の父と死後の父を結びつける回路をようやく見出すことができた。2003〜13年に撮影した父のポートレートには、すでに死の影が色濃くあらわれており、逆に2017年撮影の遺骨の写真は光のなかを漂う生きもののように見えてくるのだ。
本書『虚の胞衣』(うろのえな)は、その二つのシリーズをカップリングした写真集である。生と死という二つの世界を、コインの裏表のように見ようとする中川の意図を、両シリーズを左開きと右開きにシンメトリカルに配置した写真集の構成でしっかりと実現している。岡田奈緒子+小林功二(LampLighters Label)の端正で隙のない編集・デザインも見事な出来栄えだ。本書は中川にとって、写真家としてのスタートラインというべきだろう。このテーマに匹敵するだけの、広がりと深みを持つ作品を産み出すのは、けっこうハードルが高そうだが、ぜひそのことを期待したい。

2020/07/23(木)(飯沢耕太郎)
坂上行男『水のにおい』

発行所:蒼穹舎
発行日:2020年6月29日
本欄で以前、同じ蒼穹舎から刊行された松谷友美の写真集『山の光』を取りあげたとき、同社の出版物のクオリティの高さは認めるものの、やや引き気味に距離をとって、淡々と目の前の風景や人物をカメラにおさめていくスナップショットのスタイルが、「居心地のよい場所」に安住しているのではないかと述べたことがある。1951年生まれの坂上行男が、生まれ育った群馬県邑楽郡明和町の風物を撮影した写真集『水のにおい』も、やはりそんな蒼穹舎の出版物の範疇にぴったりとおさまる。とはいえ、前に書いたことと矛盾するようではあるが、坂上の写真集をめくっていくと、これはこれである意味必然的な、日本の風土と写真家たちとの関係のあり方に即した営みなのではないかと思えてきた。
明和町は「鶴舞う形の群馬県」とうたわれた群馬県の、くちばしの部分に位置する「利根川と谷田川にはさまれる田園の町」である。いわば典型的な日本の田舎町なのだが、その季節ごとに姿を変える景色を細やかに写しとった写真群を目で追ううちに、何とも言いようのない懐かしさと切なさが込みあげてくる。そんな感情を呼び起こす要因となるのは、「水のにおい」ではないだろうか。坂上の写真には、大小の川や用水堀だけでなく、雨上がりの道、濡れそぼった植物などがよく写り込んでいる。湿り気のある大気の感触は、誰でも身に覚えのあるものだろう。蒼穹舎風のつつましやかで受容的なスナップショットのスタイルが、カラープリントに「水のにおい」を封じ込むやり方として、とてもうまくいっていることを認めないわけにはいかないだろう。
2020/07/23(木)(飯沢耕太郎)
内藤礼『空を見てよかった』

発行所:新潮社
発行日:2020/03/25
本書は、美術家・内藤礼による「ほぼ」言葉のみの作品集である。過去の展覧会で発表されたステートメント、文芸誌や新聞に寄せた折々の短文、それから本書のための書き下ろしや未発表の私記が、時系列順にではなく、全体でひとつの流れをつくるように配されている。「ほぼ」と言ったのは、表紙と本書の中ほどに計二点、《color beginning》という絵画作品がひそかに印刷されているからである。
何も知らずに本書を手に取った読者は、これをどのように読めばいいのか、少なからず戸惑うにちがいない。これは美術家の手による詩集ではない。まして、その作品の背後にある思想を明快な言葉で綴ったエッセイでもない。ここにあるのは「言葉」である。そして、言葉がこのように言葉として差し出されるというのは、今日において驚くべきことである。
これは詩集ではないと言ったが、それはもちろん、ここにある言葉の連なりがポエジーを欠いているという意味ではない。むしろ、行分けをふんだんに用いた本書の端々から受ける第一印象は「詩」以外の何ものでもあるまい。げんに、本書をめくり始めて数頁のうちに、「ただそこにじかにふるえ/すべてそのちからふるわし」(8頁)といった一定のリズムをもつ詩的なセンテンスが、次々と目に飛び込んでくる。ゆえに形式的に言えば、これらの言葉を詩とみなすことこそ、もっとも穏当な選択肢ではないかと思える。
他方、ここに書かれていることを、作家その人の制作論として読むことも可能だろう。たとえばこんな一節がある──「ここにはもうすでに空間があるというのに、なぜそれに触れようとしているのだろう。なぜものを置こうとしているのか。なぜものをなのか。変化をなのか。そうではない。この世界に人の力を加えることがものをつくるという意味だと言うのなら、私はつくらない」(26頁)。「作るという考えは傲慢だといつしか思うようになっていた。長い間、作ると言うことも書くこともしなかった。モノはそれ自体で生まれてくるのに、人が作るとはどうしたことだろう」(140頁)。
しかし以上のどちらなのか、と問われれば、そのどちらでもあり、どちらでもないというべきだろう。第一に、ひとつひとつのテクストにはそれらしきタイトルが一切ない。巻末の初出一覧を見ても、その書き出しが並べられているだけで、どれひとつとして「タイトル」を与えられた文字列はない。だとすると、やはり本書は丸ごとひとつの言葉の集合だと考えるべきなのだろう。
本書ではひらがなが多用されている。はじめ、それに対してわざとらしい印象を抱く読者もいるかもしれない。だが、わたしが繰り返し本書をめくるなかで感じたのは、いささか独特な漢字かな開きと、余白の取り方によって誘導された、あまり経験したことのない視線と思考の運動であった。それによって、ここにある言葉との距離がふと近くなったり、遠くなったりする。とはいえ、おそらくこれは読み手に対しても一定の調性を求めるプロセスであるため、誰もがそのような感慨を持てるものかどうか、正直なところ評者にもわからない。ただひとつ言えることがあるとすれば、この感覚は内藤礼の作品が空間中に立ち上げる独特な磁場と、きわめて類似しているということである。
現在、石川県の金沢21世紀美術館では、内藤礼の2年ぶりの個展「うつしあう創造」が開催されている(8月23日まで)。会期終了後に刊行されるそのカタログのなかで、評者はまずその作品がもたらす「驚き」について論じようと思った。そこで書いたことと、この場で本書について書いてきたことは、ほとんど同じことを言っていると思う。その驚きとは、こちらの意表を突くような暴力性をともなった驚きではなくて、長時間そこに身を浸すことにより徐々に湧き上がってくる、いわば遅効性の驚きなのである。
2020/07/27(月)(星野太)
佐々木敦『これは小説ではない』
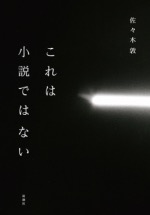
発行所:新潮社
発行日:2020/06/25
すでに広く知られているように、批評家・佐々木敦は今年に入って「批評家卒業」を宣言し、『新潮』4月号に「半睡」という初小説作品を発表した。今後も批評的なテクストは書きつづけるとのことだが、これまで著者がこだわってきた「批評家」の看板を下ろすという宣言は、わたしを含めた以前からの読者に驚きをもって受け止められた。
その理由や心境については、すでにいくつかのインタビューや著書のなかで明らかにされているため、ここで評者がわざわざ贅言を費やすにはおよばない。いずれにしても、佐々木にとって大きな節目となる今年、これまでの仕事を総決算するかのように、続々と新著が刊行されている。演劇批評集としては意外にも一冊目に当たる『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン、6月)、これまで単行本未収録だったさまざまなジャンルの文章を集めた『批評王』(工作舎、8月)、雑誌『群像』での連載をまとめた『それを小説と呼ぶ』(刊行予定──『これは小説ではない』のあとがきを参照のこと)、さらに佐々木が編集長を務める文芸誌『ことばと』の創刊号(書肆侃侃房、4月)まで含めると、隔月以上のペースで何かしらの本が刊行されている。
本書『これは小説ではない』も、そうした一連の刊行ラッシュに連なるものである。しかしこの書物こそは、どうあってもこの著者にしか書けない、紛れもない主著のひとつと言って差し支えないように思う。本書のもくろみは、おおよそ次のようなところにある。すなわち、「小説とは何か」「小説に何ができるか」ということをはじめから大上段に論じるのではなく、「映画は小説ではない」「写真は小説ではない」「音/楽は小説ではない」「演劇は小説ではない」──というふうに、ほかの芸術ジャンルの可能性と限界を浮き彫りにしていくところから、来たるべき小説のポテンシャルを照射していこうという構えである。これまで「横断」ならぬ「貫通」をモットーとしてきた著者らしく、異なるジャンルを論じたどの章も、これ以外にないと思わされるような例示と分析で溢れている。
だが、おそらくこれだけでは、事の半分しか説明したことにならない。第1章「ラオコオン・エフェクト」に見られるように、本書はレッシングからグリーンバーグにいたる近代の「詩画比較論(パラゴーネ)」の基本を押さえるところから始まっている。しかし本書はそこから、各ジャンル(あるいはメディウム)の固有性とは何か、という安易な本質論にはけっして赴かない。本書の考察を導くのは、あくまでも具体的な作品である。しかも特筆すべきことに、その多くは必ずしも名作揃い(いわゆる「古典」)というわけではなく、著者が連載中に接した、あるいは過去に接してきた有名無名の作品群なのである。
かねてより、著者はたとえ大きな連載であっても、その時々に見聞した作品の「時評」を心がけているという旨のことを語っていた。それは過去の著書をひもといてみれば明らかだろう。本書もまた、紛れもなくそのような一冊である。そして、これだけ多くのジャンルにまたがるパラゴーネを遂行しつつ、それを同時に時評としても成立させることができるのは、佐々木敦を措いてほかにいまい。その意味で、本書は『新しい小説のために』(講談社、2017)や『私は小説である』(幻戯書房、2019)をはじめとするここ数年の小説論に連なる一冊であるとともに、映画から音楽へ、文学から演劇へと不断に軸を移してきた著者の、30年におよぶ批評活動の集大成でもある。
2020/07/27(月)(星野太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)