artscapeレビュー
2016年05月15日号のレビュー/プレビュー
21世紀琳派ポスターズ ─10人のグラフィックデザイナーによる競演─

会期:2016/04/04~2016/05/13
京都dddギャラリー[京都府]
昨年「琳派誕生400年記念」で盛り上がった京都。本展は、グラフィック・デザイナー10人(浅葉克己、奥村靫正、葛西 薫、勝井三雄、佐藤晃一、永井一正、仲條正義、服部一成、原 研哉、松永真)が「琳派」からインスピレーションを受けて制作したポスターを一堂に展示し、21世紀のデザインに流れる琳派の水脈を探るもの。出展作は4連の屏風形式で統一されて、個性ある競演となっている。グラフィック・デザインに日本の美意識および「花鳥風月」を表象することは、田中一光が独自に追求してきたところのものだが、本展の面白味は各デザイナーの多様な「琳派」解釈が見られるところ。例えば永井一正は、金地の背景に緑で山並みの景観を簡潔に表現しつつ、ユーモアあふれる表情の動物たちを白で効果的に配置する。宗達の《風神雷神図》を思い起こさせるような抑制した色使いで、琳派を題材としながらも、それをさらに掘り下げた普遍性を色と形で追求している。その一方で服部一成は、大和絵以降に伝統的な山の連なりを曲線と線を用いて、ポップでグラフィカルな現代的表現にアレンジしている。また原研哉は、金箔を実際に貼って撮影した後景に、楕円形の海の月と有機的な形態のクラゲを浮かび上がらせ、琳派のもつ装飾性を昇華している。日本の歴史的伝統をテーマにしながら、現代のデザイン感覚の洗練と豊かな広がりを見ることができる。[竹内有子]
2015/04/14(木)(SYNK)
MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事
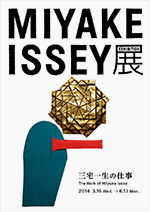
会期:2016/03/16~2016/06/13
国立新美術館[東京都]
1970年の三宅デザイン事務所設立から現在、そしてその未来まで、三宅一生の仕事を展望する大規模な展覧会。3つに分かれた最初のセクションAは70年代。綿ジャージを素材に皆川魔鬼子のプリントデザインを施した《タトゥ》を先頭に、ファッションショウのランウェイのように細長い展示室に服が1列に並ぶ。セクションBは80年代前半。繊維強化プラスチックを用いた《プラスチック・ボディ》、籐と竹を素材とした《ラタン・ボディ》などのシリーズだ。この2つの展示デザインは吉岡徳仁。セクションAの人体は段ボール、セクションBの人体は透明な樹脂でできており、いずれも三宅一生の服を象徴する「一枚の布」をコンセプトに、一枚の板をレーザーでカットしたものだという。セクションCは80年代以降の仕事で、素材づくりからはじまり技術の開発を行ないながらデザインを進める三宅の服づくりは、やがてプロダクトデザインの領域へと拡大する。その代表が「製品プリーツ」や「A-POC」、そして「132 5. ISSEY MIYAKE」だ。展示デザインは佐藤卓。縮小サイズの「132 5. ISSEY MIYAKE」をトルソーに着せる体験コーナーは、やはり佐藤卓が手がけた21_21の「デザインあ」展を思い出させる。この展示室にはプリーツ・マシンが設置されていて、田中一光のポスターモチーフを用いたプリーツの製作が毎日実演される★1。映像インスタレーション制作は中村勇吾。他に合計50分ほどの映像上映がある。
他のデザイナーの展覧会にどれほどの報道陣が集まるのか知らないが、300人程度を収容できる講堂が記者でいっぱいになったといえば、この展覧会への注目度がうかがわれよう。三宅一生は間違いなくスターデザイナーの一人だ。スターの背後には、その仕事を支える多くの人びとがいる。三宅一生が他の多くのスターと異なるのは、その仕事においてスター本人ばかりではなく、協働者たちにもスポットライトが当てられる点ではないだろうか。たとえば今回の展覧会の記者説明会には、企画を担当した北村みどり氏、デザインを担当した佐藤卓氏、吉岡徳仁氏が企画と展示について語り、三宅氏は主にそれを横で聞いている。三宅氏と青柳正規氏が発起人となった「国立デザイン美術館をつくる会」のシンポジウム(2012年)のときも、デザイナーたちのディスカッションを見守っていた三宅氏の姿が印象に残っている。
1987年から99年までコレクションの写真を手がけたアーヴィング・ペン氏との仕事においては、ペン氏の発想の妨げとならないよう撮影に立ち会うことをしなかった。それは「自分自身が堕落しないように厳しい評価をしてくれる人を必要としていた」からだという★2。協働者はアーティストやクリエーターに限らない。紙衣のための和紙工房、日本の毛織物であるホームスパンの工房、プリーツ加工の会社など、素材のつくり手、技術の担い手も積極的に紹介される。外部とのコラボレーションだけではない。仕事はチームで進められる。新しいアイデアもチームから生まれる。チームによって若い人を育てる。本展のタイトルは「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」だが、展示のいたるところに協働とチームによる仕事を確認できる。しかしおそらく最大の協働は来館者とのものだろう。スタッフはもちろん、来館者にもISSEY MIYAKEの服を着ている人が多い。「作品として発表しても、人が使わない限りデザインではない。そして、使い込まれたデザインはデザインした人のものではなく、使った人のもの」★3なのだ。本展図録の序文で三宅氏はデザインミュージアムの構想に触れて次のように記している。「この二十年来、安藤忠雄さんや青柳正規さんはじめ、共鳴してくれるたくさんの人々とデザインミュージアムの設立を呼びかけているのは、人づくりと、世界各都市とを連携するため」だという。服をつくること。服を売ること。展覧会をつくること。ミュージアムをつくること。すべては人をつくり、人と人を結び、未来をつくるためにある。[新川徳彦]
★1──11:00~12:00。金曜日は11:00~12:00、15:00~16:00、18:00~19:00。
★2──「三宅一生インタビュー 未来への提言」(『美術手帖』2011年12月、35頁)。
★3──柳宗理との対談「アノニマウスデザインに向かって」(1998年。森山明子『デザイン・ジャーナリズム─取材と共謀』美学出版、2015年7月、178~182頁に再録)。

会場風景 左:セクションA 右:セクションB

会場風景 セクションC
2016/03/15(火)(SYNK)
中里和人「惑星 Night in Earth 」

会期:2016/03/21~2016/04/02
巷房[東京都]
中里和人の新シリーズ「惑星」は高知県、和歌山県、三重県、千葉県など、黒潮の流れに沿うようにして、日本の沿岸部にカメラを向けている。写っているのは、夜の月明かりの下、波が打ち寄せる岩場の光景だ。それらは、たしかに「遥か遠くの宇宙を観測する望遠鏡や人工衛星から」送られてくる「新しい惑星の姿」のようでもある。
中里は代表作の『小屋の肖像』(メディアファクトリー、2000年)のように、これまで人間の営みがなんらかのかたちで刻みつけられた風景を撮影し続けてきた。ところが今回の「惑星」には人の気配は感じられず、無機的かつ即物的な眺めが定着されている。中里は1978年に法政大学文学部地理学科を卒業しているから、岩盤や地層を意識することは特に不自然ではないが、新たな方向に踏み出していこうとする意欲作といえるだろう。とはいえ、そのような「裸の惑星空間」は、奇妙なことにどこか懐かしい「親近感」も感じさせる。もしかすると、波が打ち寄せる夜の海辺の眺めが、われわれの集合的な無意識に働きかけるのかもしれない。太古の昔、ふと住居の海辺の洞窟を出ると、こんな光景が目の前に広がっていたのではないかとも思ってしまうのだ。
今回の展示は、東京・銀座、奥野ビルのギャラリー巷房の3階、地下1階、階段下のスペースを使って行なわれた。3階と地下1階のギャラリースペースでは、大小の写真プリント20点が額装されて並んでいたが、階段下では映像作品をプロジェクションしていた。静止画像と動画を併置することはそれほど珍しくはなくなってきたが、中里のような風景中心の写真家にとっては、やはり新たなチャレンジと言えるだろう。画像と音響効果(波の音、ノイズ系の音楽)がうまく融合して、効果的なインスタレーションとして成立していたと思う。
2016/03/21(月)(飯沢耕太郎)
重森陽子展

会期:2016/03/22~2016/04/03
ギャラリーマロニエ[京都府]
重森陽子は動物や人間の姿を捉えた陶オブジェを制作する作家だ。その特徴はスピード感を重視したラフな造形にあり、やきものでドローイングをしているような風情を持つ。ところが今回、彼女の作品は大きく変化した。ジオラマのような情景描写を行なっていたのだ。それらは山水画を立体化した「3D山水」だという。彼女は以前から「陶画塾」という絵付けの勉強会に参加しており、山水画を学ぶうち、それらを立体化したいと思うようになった。ドローイング風の造形はこれまでと同様だが、筆者が感心したのは「3D山水」というアイデアである。ほかの陶芸家を巻き込んでいけば、ひとつの分野を形成できるかもしれない。本人がどれほどの展望を描いているか不明だが、大きな可能性が感じられる個展であった。
2016/03/22(火)(小吹隆文)
アート・アーカイヴ資料展XIII「東京ビエンナーレ’70再び」
会期:2016/02/22~2016/03/25
慶應義塾大学アート・スペース[東京都]
中原佑介(1931-2011)は、京都大学の湯川秀樹のもとで理論物理学を学んでいたが、在学中の1955年、評論「創造のための批評」が『美術批評』誌の評論募集で一席に選出されたことを契機に上京、本格的に美術評論家としての活動を始めた。その出発点からちょうど15年後の1970年、中原は東京都美術館を会場に「第10回日本国際美術展 人間と物質」展を企画した。近年大きな注目を集めているこの伝説的な展覧会の全容を、残された資料や関係者へのインタビューなどをとおして解明した調査研究の成果を発表したのが、本展である。
会場に展示されたのは、したがって「人間と物質」展に出品された作品そのものではなく、それらの作品を設置する作業を記録した写真や会場内の空間を再現した縮小模型、そして展覧会の図録など、おびただしい資料群。調査研究の焦点が、とりわけ誰の作品がどこに設置されていたのかという点を正確に把握する側面に当てられていたせいか、縮小模型と記録写真を併せて見ると、未見の展覧会を垣間見るかのようなイリュージョンを楽しむことができた。会場で配布された50頁に及ぶ小冊子も、資料的価値が高い。
注目したのは、この展覧会のチラシに掲載された短い言葉。なぜなら、それらはこの伝説的な展覧会の核心をみごとに凝縮しているように考えられるからだ。中原自身によるのか、あるいは事務局によるのか、次のような一文がある。
「出来合いの作品を並べる時代は過ぎました。世界美術の先端をゆく参加作家のうち3分の2が東京にやってきて、ロープをまき、布を敷きつめ、灰を盛り上げ、水を汲む。この大いなるナンセンスは、美術よりも音楽よりも文学よりもはるかにおおらかで、しかもそれらすべてを包み込んだ今日の芸術といっていいでしょう」。
事実、クリストは1階の彫刻室の全体を175枚の塗装用布で梱包し、ライナー・ルッテンベルクは灰を盛り上げた2つの山を250本の細い鋼鉄の棒でつないだ。重要なのは、中原がそのようなナンセンスを今日の芸術として、言い換えれば、最先端の現代美術として位置づけている点である。が、それだけではない。そのチラシには以下のような一文が続く。
「書物を読む人捨てた人、テレビを見る人飽きた人は、ためらわずに上野に行ってみてください。美術がこれほど身近に感じられることに、驚かずにはいられないでしょう」。
意外なことに、中原にとってナンセンスは美術に縁のない庶民でもリアリティーを感じることができるような類の美術だった。こうした企画者の見方が、鑑賞者の見方と必ずしも照応していなかったことは、今日よく知られている。本展では特に触れられていなかったが、「人間と物質」展の開催当時の評判は必ずしも芳しいものではなかった。中原はその批判的な言説をみずから分析している(『中原佑介批評選集第五巻「人間と物質」展の射程』現代企画室+BankART出版、2011)。「この新しい美術家たちが現実に対して鋭い発言を投げかけようと意図しながら、あまりにも観念的な世界に自ら閉じこもり、観衆にむしろ背を向けた姿勢を示しているのではないか」(小川正隆)、「身動きできずに、立ち尽くした。極北化願望のここまでの徹底。徹底の果ての、あやうく狂気。これほど、玩具製造精神に似て、しかもこれほどそれに遠いものがあるであろうか」(宗左近)、「彼らの意識にあるのは連帯なのであろうが、その秘儀的なジェスチュアからはおおらかな精神の広場を望むべくもない」(野村太郎)などなど。このような言説を手がかりにすれば、中原の希望的観測はおおむね外れたと言ってよい。
だが、そのような結果は火を見るより明らかだったはずだ。考えたいのは、なぜ中原は対話不在という謗りを免れないことがわかりきっていたナンセンスを、あえて庶民のリアリティーと直結させたプレゼンテーションを企てたのかという点にある。仮にそれが方便だったとしても、中原の真意はどこにあったのだろうか。
ひとつには、ラディカリズムを極限化させた60年代の反芸術への反省があったのかもしれない。それは、日常的な事物や廃物を素材として利用した点では庶民のリアリティーと共振したと言えるが、とりわけ反芸術パフォーマンスのハプニングや儀式は、生身の肉体を大々的に露出させたがゆえに隘路に陥り、ほどなくして自滅せざるをえなかった。もしかしたら中原は、そのようなラディカリズムの重心をあえて物質に傾けることで、それを転位させようとしたのではなかったか。
「人間と物質」展が、反芸術に代表される60年代の美術ともの派に代表される70年代の美術の結節点として考えられることは疑いない。だが、そこでいったいどのような価値観の転換があったのか、その内実については依然としてわからないことが多い。必要なのは、「人間」と「物質」のあいだの「精神」を解明することである。
2016/03/22(火)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)