artscapeレビュー
2011年08月01日号のレビュー/プレビュー
KATHY's "New Dimension"
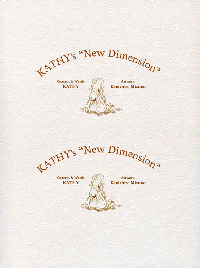
会期:2011/06/03
ピンク、ブルー、イエローの衣装を身にまとい、ブロンド髪で顔には黒ストッキングをかぶっている(かに見える)、ユニークなルックスの三人組KATHY。「きもかわ」というか、ホラーと乙女チックの両方を重ね合わせたイメージと、「指令者が課してくる任務の遂行として踊る」といったコンセプトとで、これまでコンテンポラリー・ダンスの世界に限らず、さまざまな場で話題を振りまいてきた彼女たちが、6月に本を出した。タイトルにあるように「新しい次元」でのダンスがテーマ。驚くのはこの「次元」という言葉が比喩として用いられているのではないということ。宇宙物理学などを援用しながらの文章では「みえないダンスの世界へ」「マルチバース(多元的宇宙)においてのあたらしいダンスを考える」などの言葉が踊る。「新しい」なにかがここに胎動していると感じられはする、とはいえ、正直まだ謎めいた部分も多い。おそらく、本書を発端に展開される今後の活動を通して真意が明らかにされていくことだろう。現時点で十分明白に感じられるのは、「ダンス」という言葉で通念上考えられているなにかとは異なるなにかを希求する強い思いがKATHYのなかに沸き立っていること。なるほど、「立てない身体」から出発した土方巽が「床」の存在を疑ってみせたように、新しいダンスは、ぼくたちの通念を疑うところからしか始まらないに違いない。
「みえないダンス」の可視化に寄与しているのは、水野健一郎によるイラストレーション。肉体をもって踊ることが(通念上の意識において)三次元のダンスであるとして、一次元引いた(二次元の)イラストレーションによってこそ、三次元のダンスの限界の「先」が示唆できる、という事態に驚かされた。そうか、イラストレーションとしてのダンスか! ダンスは肉体で踊られなくても作品化できるのだ! 水野の絵には、ときにハンス・ベルメールの素描を連想させるところがあり、身体や空間のイメージが拡張されるスリルに満ちている。その意味で、水野の作品集『Funny Crash』をあわせて読むことをお勧めする。ちなみに添付されたDVDに収録されているKATHYの最新映像作品によっても十分予感を与えてくれていることなのだけれど、今後のKATHYや彼女たちと水野健一郎とのコラボレーションによって、彼女たちの謳う「あたらしいダンス」が確実なかたちを帯び、世界を震撼させるときがくることを待望せずにはいられない。
2011/06/03(金)(木村覚)
堀内誠一──旅と絵本とデザインと

会期:2011/04/23~2011/06/26
うらわ美術館[埼玉県]
『アンアン』『ポパイ』『ブルータス』などのエディトリアル・デザインを手掛けた堀内誠一(1932-1987)の多彩な仕事を、アートディレクター、絵本作家、旅行家という三つの側面から紹介する展覧会。2009年7月に世田谷文学館からスタートして各地を巡回し、今回うらわ美術館で2年間の旅を終えた。世田谷文学館を訪れたときは彼のデザインの仕事の幅の広さとヴォリュームとに圧倒されたが、今回は絵本作品に見られる多様な画風が印象に残った。多くの絵本作家は──少なくとも短期には──画風を変えないし、絵本の編集者も読者も作家独自のタッチを期待していることと思う。なぜ、堀内はかくも多彩な表現で絵本を制作したのであろうか。
絵本作家マーシャ・ブラウンは、作品ごとに画風を変える理由を問われて、「物語が違うから」と答えたという。木村帆乃氏は、この話を堀内もたびたび指摘していたとし、「この姿勢はそのまま堀内誠一自身にも当てはまるだろう」とする(木村帆乃「パロディの美学」[『堀内誠一 旅と絵本とデザインと』平凡社、2009、88頁])。もちろん、それは絵本作家としてのひとつの方法論なのかもしれないが、編集者の立場からすれば別の作家に頼むという選択肢もある。そう、「編集者・堀内誠一」が彼の仕事すべてに共通するキーワードなのだ。堀内は最初から多様な画風を目指していたのではない。しかし、「こんな絵が欲しいと思っても、なかなかぴったりした絵を描いてくれる人がいない。それならっていうんで自分で描くようになった」(堀内誠一『父の時代私の時代』、マガジンハウス、2007、163頁)のである。彼の画風が多様であるのは、絵本作家・堀内が編集者・堀内の依頼に応えた結果と言えないだろうか。
堀内の多彩な仕事の背景には、全体を俯瞰し、内容に合わせて最適な素材、人材の組み合わせを考える編集者としての視点がつねにあり、編集者としての堀内の要求に、デザイナーとしての堀内、絵本作家としての堀内、紀行作家としての堀内が応えていく構図が見える。そのようにしてでき上がった作品は、一つひとつを比べてみるとその違いに目が行くものの、全体を通してみると間違いなく堀内誠一の仕事である。「どんな仕事でも、その注文に合わせながら、どこか自分の分も表現しているんだろうってのが僕のやり方だったのかもしれませんね」(同、163頁)という言葉に、多様な表現の背景にある堀内の一貫した精神が見て取れるのである。[新川徳彦]
2011/06/16(木)(SYNK)
岸雪絵 展「a patched scene」

会期:2011/06/21~2011/07/03
ギャラリー恵風[京都府]
画廊のふたつの壁面にまたがる絵巻物風の大作に驚かされた。街中の風景を元にした版画だが、一つのモチーフが左右反転して繋がっているなど仕掛けが満載で、異世界に迷い込んだような気分になれる。彼女はこれまで小売店のショーケースに並んだ商品などを主なモチーフとしており、屋外を描くのは珍しい。本展で新たな可能性が示されたので、今後は作風が一層広がるかもしれない。
2011/06/22(水)(小吹隆文)
今、できること 京都造形芸術大学一汁一菜の器プロジェクト

会期:2011/06/21~2011/07/10
ギャラリー H2O[京都府]
東日本大震災の被災地で、人々が発泡スチロールや紙の食器を使っていることを知った京都造形芸術大学陶芸コースの学生・通信学生たち17名が、約800個の丼をつくって被災地の仮設住宅に贈った。本展はそのサンプル展示ともいうべきものだ。簡易な量産品を想像していたのだが、上質な1点ものが並んでいたのは良い意味で驚き。一汁一菜分が1セットになっており、それらを包む包装(染色品)も上品な仕上がりだ。これなら私が普段使っている食器より遥かに上等である。少しでも被災地の人々に役立てばと思う。
2011/06/22(水)(小吹隆文)
チェルノブイリから見えるもの

会期:2011/05/03~2011/06/25
原爆の図丸木美術館[埼玉県]
1986年のチェルノブイリ原発事故の後、いわゆる「死の灰」に汚染された地域に立ち入り、そこで生活を送ることを決意した人びとを撮影した広河隆一と本橋成一の写真、そして彼らを描いた貝原浩のスケッチ画を見せる展覧会。福島第一原発による放射能汚染の実態が徐々に明らかになりつつある今、その脅威のもとで私たちはいかに生きるのかという問題を、チェルノブイリという前例から考えさせる、まさしく時宜を得た企画展だ。震災以後、「被災者の心情への配慮」を理由に「原爆を視る 1945-1970」展の開催をとりやめた目黒区美術館とはじつに対照的だが、丸木位里・俊夫妻による《原爆の図》シリーズを常設展示している同館は、やるべき仕事をきっちり果たしたという点で、高く評価されるべきである。三者のなかでも、とりわけ印象深かったのが貝原浩のスケッチ画。現地の風物や人びとの日常、そして文化を和紙に水彩と墨で丹念に描いた絵がなんとも味わい深い。しかも、それらの余白に詳細な解説文が書きこまれているため、時間性を伴った絵本や絵巻物のように、見ているうちにぐいぐいと画面に惹きこまれてゆく。画と文が有機的に一体化しているという意味では、先ごろ世界記憶遺産に認定された山本作兵衛の炭鉱画に近いといってもいい。貝原が目撃したのは、放射能に汚染されたことを知りながら、それでも故郷で生きることを決意した人びとの、たくましくも哀しい心持ちだ。それが彼らの郷土愛に由来していることはまちがいない。けれども、貝原の画文を見ていると、究極的にはそれが人間の「生」が本来的に自然と密着しているという厳然たる事実にも起因していることに気づかされる。大地と空間と水なくして生命が成り立たないことを身体的に知っているからこそ、たとえ汚れてしまったとしても、彼らはその土地で生きることを選んだのではなかったか。色とりどりのスカーフを頭に巻いた老女たちを指して、「あの太い足にはきっと大地の精気を吸い上げる力があるのだと思う」と記した貝原の視線は、そのことを鋭く見抜いていたのだ。貝原浩のスケッチ画は、『風しもの村から──チェルノブイリ・スケッチ』(平原社、1992年)で見ることができる。
2011/06/22(水)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)