artscapeレビュー
2014年08月15日号のレビュー/プレビュー
絵画の在りか the way of PAINTING

会期:2014/07/12~2014/09/21
東京オペラシティアートギャラリー[東京都]
相変わらず展覧会で絵画はよく見かけるけど、「絵画の現在」を特集した企画展は意外なほど少ない。ほとんどないといってもいい。記憶にあるのは、06年の「エッセンシャル・ペインティング」と10年の「絵画の庭──ゼロ年代日本の地平から」くらい。どちらも大阪の国立国際美術館の企画で、しかも前者は欧米の作家のみだったため、日本人のもやれという声に押されて後者を企画したと勝手に解釈しているのだが、とにかくそれほど日本では絵画の展覧会が成立しにくいようなのだ。なぜか? それは本展のカタログのなかで堀元彰氏も書いてるように、絵画があまりに多様化してもはやひとつの基準では計れず、展覧会としてまとまらないからだ。だからこの展覧会も明確なテーマを打ち出すことなく、「絵画の在りか」といういささか投げやりなタイトルをつけるしかなかったのだ、たぶん。でもぜんぜん方向性が見出せないわけでもなく、わずかながら示してはいる。それは絵具や支持体など物質性の強調であり、その結果としての表象性から抽象性への傾きだ。これはよくわかる。ここに出ている24作家による約110点の作品の大半は具体的イメージを伴っているものの、いわゆる具象画とは呼べるものは少ない。たとえば小西紀行は家族の肖像を描いてるらしいが、われわれの目はなにより大胆なストロークに引きつけられる。今井俊介の絵画は幾重にも重なった旗のようにも見えるし、抽象パターンの組み合わせにも見える。五月女哲平と高木大地の作品も同じく具象的イメージと抽象パターンを行ったり来たりする。どうやら具象とか抽象とか、ポップとかミニマルとか、なんとか主義やなんとかイズムに染まらずに絵を描くことができる、いや、絵を描き続けなければならない時代なのだ、いまは。
2014/07/08(火)(村田真)
「みずのすがた わが山河 Part V」展

会期:2014/07/12~2014/09/21
東京オペラシティアートギャラリー[東京都]
こってり油っぽかったメインディッシュの後は、水々しい日本画のデザート。3分で出たわ。
2014/07/08(火)(村田真)
倉谷拓朴「Last Portrait Project」

会期:2014/06/28~2014/07/21
川崎市市民ミュージアム 1階 逍遥展示空間[神奈川県]
倉谷拓朴は2003年に東京綜合写真専門学校卒業後、横浜・黄金町にアートスペースmujikoboを開設したり、越後妻有アートトリエンナーレで「Last Portrait Project」や「名ヶ山写真館」といった企画を立ち上げたりするなど、意欲的な活動を行なってきた。今回川崎市市民ミュージアムで開催されたのは、2006年からさまざまな場所で展開されてきた、遺影写真の撮影・展示のプロジェクトである。
葬儀の席や仏壇などに掲げられる故人のポートレート(遺影写真)は、死者の記憶を共有し、後世に伝えるために重要な役目を果たしてきた。ただ、アルバムなどに貼られていた写真を複写して使うこともあり、クオリティ的には問題が多い。倉谷は、あえて生前に思いを込めてポートレートを撮影してもらうことで、遺影写真の新たな形式を模索しようとしている。これまで撮影された「Last Portrait」は、既に1000枚以上に達しているという。
倉谷はその撮影のために独自のマニュアルを作成した。カメラのレンズを見て静かに目を閉じ、気持ちが落ち着いた所で目を開ける。その瞬間にシャッターを切るというものである。目をつぶることで内省的な気分が生じ、その人物の「原型」とでもいうべき存在のあり方が滲み出てくるということだろう。たしかに、会場に展示されていた作品には、長く遺していくべき「Last Portrait」にふさわしい、威厳のある表情や身振りが写り込んでいるように思える。また、今回はモデルを募集し、7月6日、20日、21日の3回にわたって、実際に8×10インチの大判カメラでポートレートを撮影するというイベントも行なわれた(毎回10人)。このプロジェクトは、これから先も厚みを増しつつ、続いていくのだろう。それが最終的にどんな形をとっていくのかが楽しみだ。
2014/07/08(火)(飯沢耕太郎)
葛西優人「Sail to the Moon」
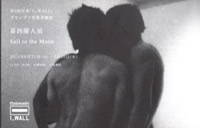
会期:2014/06/23~2014/07/10
ガーディアン・ガーデン[東京都]
2009年から開始されたガーディアン・ガーデンの「1_WALL」展(リクルート主催)も回を重ねて、既に9人のグランプリ受賞者を輩出した。今回開催されたのは、その9回目の受賞者、葛西優人の個展である(審査員は鷹野隆大、土田ヒロミ、姫野希美、増田玲、町口寛)。
男子二人によって生み出されていく性の領域を、どこか思わせぶりな写真の連なりとして提示するセンスは悪くない。大小の写真を壁面に並べていくスタイルも手慣れた感じがする。だが、どこか既視感を覚えてしまう。これはちょっと困ったことで、葛西の写真に取り組む真摯な姿勢は好感が持てるし、作品世界の構築の方向性も間違っていないにもかかわらず、着地点がどうもうまく見えてこないのだ。
顔がほとんど見えず、クローズアップが多く、断片的に切り取られた不分明な画像が並ぶ写真の構成・展示のあり方そのものを、再考する必要があるのかもしれない。別にわかりやすい写真にしなくてもいいのだが、被写体をもう少しストレートに見据えて、丁寧に撮影してもいいのではないだろうか。鷹野隆大が「彼は不器用なタイプの人間である」というコメントを寄せているが、僕にはそう思えない。少なくとも写真展の構成に関しては、器用にまとめてしまったように見えてしまう。「不器用」を最後まで貫き通してほしいものだ。
2014/07/09(水)(飯沢耕太郎)
神田開主「地図を歩く」

会期:2014/07/02~2014/07/15
銀座ニコンサロン[東京都]
ハッセルブラッドSWCで撮影された真面目な風景写真が並ぶ。神田開主(あきかみ)は2011年に日本写真芸術専門学校研究科を卒業した、まだ若い写真家だが、既に揺るぎない技術と、対象物を細やかに観察できる鮮鋭な視力を備えている。被写体になっているのは、北関東各地(群馬県、埼玉県、千葉県)の「場所と場所とを繋ぐ境界のような、そんな光景」である。その指標として、樹木、道路、池、谷などが選ばれており、そこからは何かが通り過ぎていった後のような、微妙な気配が立ち上がってくる。
ただし、その画面構成やモノクロームプリントの完成度の高さは諸刃の刃であり、ともすれば丁寧に整った写真を作り上げて満足しているように見えなくもない。いま、神田に求められているのは、この粘り強い「フィールドワーク」から何が見えてくるのかを、もっと具体的に問いつめていくことだろう。この仕事は民俗学的なアプローチにも通じそうだし、北関東の植生や地勢を、写真を通じて確認する方向に進むこともできる。埼玉県に生まれ、群馬県で育った彼自身の「記憶の光景」の再確認という側面もありそうだ。彼がめざす「地図」はいったいどんな目的で使用されるべきものなのか、今後はそのあたりをもっとしっかりと提示していってほしい。
なお、写真展にあわせて、冬青社から同名の写真集が刊行されている。端正なレイアウト(デザインは石山さつき)、堅牢な造本のハードカバー写真集である。
2014/07/09(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)