artscapeレビュー
2010年10月15日号のレビュー/プレビュー
第95回記念二科展

会期:2010/09/01~2010/09/13
国立新美術館[東京都]
初日の開館まもない時間に行ってみる。二科展は1階から3階までのレンタルスペースを独占するが、会員は1階の入口近く、会友は1、2階を占め、残りの入選者は余った場所に2段掛けでつめこまれている。入ってすぐ、1枚の絵の前に椅子が置かれ、おじいちゃんが座ってる。最長老で理事長の織田廣喜だ。なんと二科会が結成された年と同じ1914年生まれの96歳。70年前に二科展に初入選し、60年前に会員に推挙されたという「生きる歴史」。関係者があいさつし、写真を撮っていく。まるでパンダ。会場をざっとひとめぐりしてみるが、迷路のように迷ってしまう。会場構成に難があるというより、どれもこれも似たような作品ばかりなので方向感覚が狂うのだ。日の丸を描いてるやつがいたが、なんと総理大臣賞を受賞している。工藤静香は特選だ。どうやら絵の良し悪しと賞とはなんの関係もないらしい。たとえば吉井愛のように「現代アート」と呼んでもいいような作品も何点かあったが、絵画だけで約千点もの入選作品の99パーセント以上は迷路を構成する壁でしかなかった。
2010/09/01(水)(村田真)
バーネット・ニューマン

会期:2010/09/04~2010/12/12
川村記念美術館[東京都]
待望された「ニューマン展」、といえるだろうか。目の端をくすぐるようなささやかなポップがもてはやされ、画面との一対一の対話を強いられる重厚長大な抽象が敬遠されて絶滅寸前のこの時代に、なにをいまさらという気がしないでもない……が、むしろそんな時代だからこそ「待望のニューマン」でなければならないはずだ。いや実際、向こうから拒絶してくるようなニューマンの無愛想な画面を相手に対話を試みるのはツライ。でもそのツラさを通り越すといろいろ見えてくるものがあるのも事実。たとえば、赤一色に塗られていると思ったら微妙なニュアンスがついていたとか、画面を縦断する垂直線(ジップ)にもあるリズムというか規則性があるとか。そんなどうでもいいようなことに気づき始めると、今度は「なぜ絵画は平らなのか」「なぜ画面は四角いのか」「なぜ額縁がないのか」「どこまで行けば絵画でなくなるのか」「つまるところ絵画とはなにか」といった、どうでもよくない根源的な疑問が次々に降りかかってくることになる。もちろん正解があるわけではなく、自分たちでそれぞれ納得のいく答えを見つけなくてはならないのだが、じつはそれこそが「ニューマン展」の効用なのではないか。絵画とじっくり向き合い、なんでもいいから言葉を紡ぎ出してみること。これは最近、疎んじられていることである。
2010/09/03(金)(村田真)
小沢さかえ展 指先から銀河

会期:2010/09/03~2010/09/20
カフェ&ギャラリーアトリエとも[京都府]
「スコップ・プロジェクト」第三回目の企画展。いわゆるホワイトキューブではなく、黒板の壁面やガラス扉のショーケース、壁に作り付けの棚などがある会場。絵画の展示の場合はとりわけ作家を悩ませそうなスペースでもある。しかし小沢はそんな空間の特徴も見事に自らの作品世界の一要素としてとりこみ、むしろ水を得た魚のようにいきいきと、魅力的な作品空間を創出した。色とりどりのプッシュピンやマグネット、チョークなどを用い、いくつもの星図を配した黒板壁面のドローイング《夜のみた夢》には、木にもたれかかる少女や動植物なども描かれたのだが、足下を照らすスポットの下で見るこの作品は想像以上に表情豊かであり、更けゆく夜空の有様のように、見る時間帯によって印象が異なるものであった。夕方頃は特に、黒い黒板に描かれた線や光の表現が際立ち、画面に不思議な奥行きが感じられる。その反対側の凹みのある壁面にぴったりとはめ込まれるように展示された作品は、今展のために制作された幅3.6メートルの大作《指先から銀河》。描かれた少女の手のひらに載る光の粒が、星座線として画面の上方にのびているのだが、その線は見る者を幻想的な物語へと導くように、後方の黒板のドローイングのイメージとつながっていく。濃紺の夜空と、その暗闇のなかで発光するような森の植物の色彩もさることながら、画面の隅でとぐろを巻く透明な蛇の姿は特に、背景と形が解け合う不思議な趣を漂わせて美しかった。想像力を自由に駆け巡らせることは才能でもあるが、それを表現として発揮することはさらに高度な技でもある。幻想的なその世界観を遊び心いっぱいに繰り広げた今展、他では見られない個展となった。
2010/09/03(金)(酒井千穂)
入谷葉子展「縁側ララバイ」

会期:2010/08/31~2010/09/12
neutron kyoto[京都府]
現在東京で同名の個展を開催中の入谷葉子の京都での新作の発表。かつて家族と暮らした自宅やその身近な風景など、思い出のイメージを過去の写真と自らの記憶をもとに、色鉛筆による色面で塗り絵のように再現している。会場には、昔の自宅の応接間をモチーフにした大作や、墓地を描いた作品をメインに、通学電車の車窓から見える風景や子ども用のビニールプールを描いた小作品なども展示されていた。今展には過去の記憶を辿って取材に出かけ、その場で新たに撮影したという写真から描いたものもあるのだが、入谷は身体的な感覚も含め、自らの記憶のイメージと現在のありさま、そのギャップという、隔たった時間をない交ぜにして表現する。描かれるものはごく個人的な思い出であり、他人には共有できない閉鎖的な世界であるのだが、しかし入谷の作品には、いつもなんとなく気持ちが引き寄せられる。モチーフが見覚えのある道具であったりごくポピュラーな生活スタイルのイメージであったりすることや、色彩のインパクトのせいも大きいのだが、ただそれよりも、それらの記憶のイメージの断片を継ぎ接ぎするような色面の構成や画面の余白、それらのどこか不安定な印象と違和感に、見る者は共感するのかもしれないと今展で感じた。“いま”という状況が永遠ではなく、つねに変化している有限の時間にあるということ、季節や環境の変化によって知る有限の時間の切なさや美しい一瞬が共通の記憶として引き出されるのだ。
2010/09/06(月)(酒井千穂)
「冩真に歸れ」展
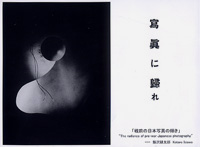
会期:2010/09/03~2010/09/19
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
第二次世界大戦前の日本の写真表現が、相当に高度な段階に達していたことは強調しておいていいだろう。東京の月刊写真雑誌『光画』(1932~33年)のグループ(野島康三、木村伊兵衛、飯田幸次郎、堀野正雄など)、関西の浪華写真倶楽部、丹平写真倶楽部、芦屋カメラクラブなどに所属する写真家たち(安井仲治、小石清、花輪銀吾、中山岩太、ハナヤ勘兵衛など)が、競い合うように前衛的、実験的な作品を発表していた。それらはひとまとめにして「新興写真」と称される。その高度な技術は、同時代の欧米の写真家たちの作品と比べても決してひけをとらない。しかも、「新興写真」を主導していたのはほとんどがアマチュア写真家たちだった。これも現在と比較してまったく違っているところで、彼らののびやかな冒険精神こそが、同時代の写真表現の最先端を切り拓いていったのだ。
今回の「冩真に歸れ」展は、東京・渋谷のZEN FOTO GALLERYを主宰するマーク・ピアソンがここ数年の間に蒐集した作品によるものである。貴重なヴィンテージ・プリントを含む作品の質はかなり高い。木村伊兵衛、島村逢江、中山岩太、ハナヤ勘兵衛など著名作家の作品に加えて、氏名不詳のアマチュア写真家のアルバムに貼られていた写真も展示されていた。風景、人物など多彩な題材だが、「新興写真」のシャープな画面構成の感覚が的確に表現されていて、なかなか面白い作品である。これを見ても、当時のアマチュア写真家たちのレベルの高さがよくわかるだろう。
なお、同時期に四谷のギャラリー・ニエプスでは、大正~昭和初期の500枚近い絵はがきによる「花電車」展(9月7日~19日)が、茅場町の森岡書店では、『光画』の実物を展示する「光画」展(9月8日~18日)が開催された。これらをあわせて見直すことで、「戦前の日本写真の輝き」をより生々しく追体験することができるのではないだろうか。
2010/09/08(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)