artscapeレビュー
2011年02月15日号のレビュー/プレビュー
今道子「今道子 展」

会期:2011/01/10~2011/01/22
巷房[東京都]
今道子が完全に復活したのは嬉しいことだ。このところプライベートな理由から作家活動があまりできなかったので、10年近く新作の発表がなかった。時々、写真ではなく現代美術の関係者から「今さんはどうしていますか?」という質問を受けることがあった。彼女の作品がむしろアート寄りに評価されてきたことのあらわれだろう。
今回の展示だが、銀座・奥野ビル3Fのメイン・ギャラリーの作品は、《蓮のワンピース》《鰯のパラソル》《こはだのシマウマ》など、食物を独特の発想でオブジェ化して撮影する以前の彼女の作風の延長線上にある。ただそのなかにも、《朽ち果てたバルコニーとphoto》《銀の消毒ケースとphoto》など、自らの記憶を辿り直すような作品が含まれているのが興味深い。ここで使われている「photo」は、父親と母親の昔の写真だ。メイン・ギャラリーの横にある、かつては美容院として営業していたという「306号室」の展示では、面白い試みがなされている。剥離しかけた壁や、美容院の鏡を画面に取り入れて《太刀魚のオーバーコート》や《海老の電話機》といった作品が撮影され、その場所でそのまま見ることができるようになっているのだ。制作の現場と鑑賞の場所を直接結びつけるという意欲的な実験である。
さらに、地下の巷房2のスペースには、これまでの彼女の世界を打ち破るような作品が並んでいた。《鰯の障子と私》《蟹の障子》では、まさに実際の障子ほどの大きさがある縦長の大きな画面に鰯や蟹が平面的、装飾的に配置されている。また「菊のドレスと青年」「お盆提灯と人形」では、これもこれまではあまり使用されなかった純和風のモチーフが取り入れられている。新たな方向に向けて舵を切り始めた今道子の作品世界の行方が、とても楽しみになる展示だった。
2011/01/10(月)(飯沢耕太郎)
池田龍雄──アヴァンギャルドの軌跡

会期:2010/10/09~2011/01/10
川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]
40年代の自画像から、50年代のシュルレアリスムや社会的テーマを描いたルポルタージュ絵画、60年代の「百仮面」シリーズと「楕円空間」シリーズ、70年代から始まるパフォーマンス《梵天の塔》、70~80年代の「ブラフマン」連作、90年代の「万有引力」シリーズ、そして2000年代の「場の位相」シリーズまで、池田は60年以上にわたり変転を重ねてきた。アヴァンギャルドらしく、ときにオブジェやパフォーマンスにも手を染めたが、一貫して絵画を捨てなかったことは時代相を考えれば驚異的ですらある。しかし併設されている同時代を生きた岡本太郎や山下菊二らの作品と比べると、はたして池田の代表作はなんだったんだろうと考えてしまう。池田の場合「これ1点」というより、シリーズもの(とりわけ初期の)で記憶に残る画家なのかもしれない。ホームランバッターではなく安打製造機というか。
2011/01/10(月)(村田真)
圓井義典「光をあつめる」
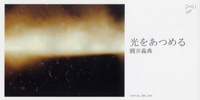
会期:2011/01/11~2011/02/26
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
柴田敏雄、畠山直哉、松江泰治、鈴木理策など、それぞれスタイルは違っていても、中判~大判カメラを使って「風景」を緻密に描写する写真家たちの系譜が1980年代以来途絶えることなく続いている。それは明らかに日本の現代写真の重要な流れを形成しているのだが、圓井義典もそこに連なる作家といえるだろう。彼は2000年代以降「自分の暮らす世界、とりわけこの日本という国を自分の目で見て回りたい」という意欲的なプロジェクトを展開している。その成果は「地図」(2000~05年)、「海岸線を歩く──喜屋武から摩文仁まで」(2005~08年)といったシリーズにまとまり、個展やグループ展で発表されてきた。
今回展示された新作「光をあつめる」は、これまでの作品とは一線を画する意欲作である。ちょうど「海岸線を歩く──喜屋武から摩文仁まで」を制作するため沖縄の旅を続けていた途中で、カメラのピントグラスに光が突然飛び込んできたのだという。それを「何ものをも名指しえない、原初の光」であると感じとった彼は、光そのものを定着することに取り組んでいった。ピントをわざとはずした画面に捕獲された光は、点、塊、渦巻きとさまざまな形に変容し、手応えのある物質感を感じさせる。このチャーミングな作品群が、これから先どんな風に展開していくかが楽しみだ。なお、展覧会にあわせて写真集『圓井義典 2000-2010』(私家版)が刊行された。3つのシリーズを分冊で木箱におさめた、すっきりとした造本(アートディレクション=中新)の写真集である。
2011/01/11(火)(飯沢耕太郎)
中平卓馬「Documentary」

ShugoArts[東京都]2011年1月8日~2月5日
BLD GALLERY[東京都]2011年1月8日~2月27日
中平卓馬が清澄白河のShugoArtsと銀座のBLD GALLERYで、ほぼ同時期に写真展を開催している。作品そのものは2004~2010年に撮影した縦位置、カラーのスナップからセレクトし直したもので、既発表のものもあり、新たな展開というわけではない。というより、2000年代になって中平の撮影と発表のスタイルはほぼ固定されている。僕はどちらかといえば、スタイルの固定化に対しては否定的なのだが、中平の場合はそれがあまり気にならない。1976年の急性アルコール中毒による逆行性記憶喪失からのリハビリの過程において、彼が選びとった写真のあり方は、文字通りの「原点復帰」であり、これ以上動かしようがないものに思えるからだ。「原点」というのは、あらゆる写真家にとってのそれということでもあり、誰もが彼の作品を見れば、カメラを最初に外界に向けた「はじまり」の日のことを思わないわけにはいかないだろう。そこにあるすべてがみずみずしく、自らの存在の光を発するように輝き、世界は生命の波動に満たされている。それをカメラで捉え、定着していくためのやり方を、中平は揺るぎないものとしてしっかりと確立したということだ。
ただそれを実行していくためには、被写体にまとわりつくあらゆる先入見や意味づけから自由であり続ける特殊な能力が必要だ。よく「子どもの目」とか「原始人の眼差し」といった言い方をするが、それは口でいうほど簡単なものではない。中平のようにやや普通ではない経験をくぐり抜けてこないと、なかなかそんな境地に達するのは難しいだろう。そういう意味では、彼のいまの状況そのものが奇跡ではないかと思えてくる。たとえば、彼がよく撮影する看板や標識──「四国讃岐手打うどん」「山吹(八重)」「日吉神社はこの先です」「と金[SUNTORY]」といった文字をどう解釈すべきなのか。これらの言葉は、何か特定の意味を担っているというよりは、現実世界における役割から解放されて、それ自体が奇妙な存在感を発して浮遊しているように見えてくる。言葉(文字)ですらも、中平のアニミスム的といえるアンテナによって、それが本来備えている「言霊」を回復しているように思えるのだ。
二つのギャラリーの展示の印象の違いも興味深かった。ShugoArtsでは90×60センチに大きく引き伸ばされた作品24点が、きちんと等間隔に並んでいた。BLD GALLERYの方は30×20センチのやや小ぶりなプリント150点あまりが、壁に2段に貼り付けてある。作品と資料としてのあり方を行き来する中平の写真行為が、それぞれの展示から見えてくる気がする。なお、Akio Nagasawa Publishingから,今回の展覧会のカタログを兼ねた堅牢な造本の写真集が刊行されている。
2011/01/13(木)(飯沢耕太郎)
レオ・ルビンファイン展

会期:2010/12/25~2011/01/29
Taka Ishii Gallery[東京都]
レオ・ルビンファイン(Leo Rubinfien)は1953年シカゴ生まれのアメリカ人現代写真家。リー・フリードランダーやゲイリー・ウィノグランドの次の世代にあたり、1970年代から都市のスナップショットを中心に作品を発表してきた。父親の仕事の関係で幼少期を日本で過ごしたことがあり、アジア諸国にもよく足を運んでいる。それらの写真をまとめたのが、代表作でもある写真集『A Map of the East』(David R Godine、1992)だ。
今回の展示は彼が過去30年間に世界各地で撮影した31点のカラー、モノクローム写真によるもの。時間と空間は無秩序に錯綜しているのだが、そこにはスナップシューターの鍛え上げられた眼力によってあぶり出された、現代社会における「世界都市」の様相が見事に写り込んでいる。ルビンファインはある展覧会のためのステートメントで、その「世界都市」という概念について以下のように説明する。
「世界都市とは自分が現在どこにいるかが特定できない空間であり、例えば、ブエノス・アイレス、デュッセルドルフと香港が各自の個性を失い、区別がつかないような場所である。また、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、それぞれの地域が持つイメージが互いのイメージに影響を与え合うと同時に、生まれ育った田舎にはないある種の自由と爽快感を体感することができる場所でもある」
つまり、ルビンファインが試みてきたのは、高度に発達した資本主義社会のネットワークに覆い尽くされた都市の環境とそこに生きる人々の姿を、偶発的なスナップショットの手法によっていかに捕獲できるかという模索だった。それがかなりの説得力を備えたイメージ群として成立していることは、今回の展示からも確認することができた。
なお、台東区蔵前の空蓮房では、彼のニューヨークで撮影された新作(モノクローム作品)を展示する「The Ardbeg」展が同時開催されている。この秋には、「9・11」以降の都市のあり方を再考する意欲作「Wounded Cities」の展示が、東京国立近代美術館で実現する予定。その活動からしばらく目を離すことができなくなりそうだ。
2011/01/14(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)