artscapeレビュー
2015年05月15日号のレビュー/プレビュー
PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015

会期:2015/03/07~2015/05/10
京都市美術館ほか[京都府]
京都で催された国際展。国内外から招聘された約40組のアーティストが参加した。見どころはウィリアム・ケントリッジをはじめ蔡國強、ピピロッティ・リストら、欧米圏で活動する著名なアーティストが数多く参加している点で、それらの作品が京都市美術館を中心に、鴨川の河畔、庶民的な団地の一室、書店などにそれぞれ展示され、美術館から街への導線を強く意識した構成となっている点も大きい。
しかし、全体的な印象は中庸というほかない。すでに多くの論者が指摘しているように、国際展や芸術祭という形式は明らかに飽和状態にあり、テーマの有無にかかわらず総花的な形式のなかで発表される作品に同時代的なリアリティを見出しにくいことは否定できないし、前述した街への導線を設定するやり方にしても、昨今の国際展の常套手段であり、いまさらとりわけ目新しいものではない。
ただし、だからといって秀逸な作品が皆無であったわけではない。京都芸術センターの旧講堂で発表された、アーノウト・ミックの《Speaking in Tongues》[異言]は、企業の社内セミナーと新興宗教の儀式を撮影した映像を並列させたインスタレーション。前者は大量の役者によるフィクションだが、後者は完全なドキュメンタリーであるという相違点が見受けられるものの、いずれも無音のまま、ある種の病的な熱狂状態を醸し出している点は通じている。
当初、舞台上の幹部社員と客席の一般社員は明確に分断されているが、拍手やハグが度重なるにつれ、次第に行事は集団熱狂状態に陥り、両者を分け隔てていた境界線は溶け合い、やがて彼らは自己啓発セミナーのような異様な雰囲気に包まれていく。何かを叫び、涙を流し、激しい身ぶりによって剥き出しにされる感情。そのような集団熱狂状態が加熱していけばいくほど、彼らの強く抑圧された暗い心のありようがありありと逆照射されるのだ。
アーノウト・ミックが示したのは、おそらく資本主義の最先端で日々闘うホワイトカラーの心の闇を、現世利益を謳う新興宗教に頼ることなくしては生存を維持することが難しいブルーカラーのそれと相通じるものとして視覚化することではなかったか。世界はますます富む者と貧しい者とに分断されつつあるが、実は両者の内面は同じような病にともに蝕まれているのだ。
アーノウト・ミックが社会的な同時代性を表わしているとすれば、芸術という概念の同時代性を自己言及的に表現しているのが、アフメド・マータルである。《四季を通して葉は落ちる》は、昨今変貌目覚ましいイスラム教の聖地・メッカの工事現場や解体現場を捉えた映像作品。天空に突き出た超高層ビルの先端での作業の高揚感や古いビルが一気に倒壊するカタルシスを存分に味わうことができる。だが、この作品の本当の醍醐味は、これらの映像を撮影したのがアフメド・マータル本人ではなく、当の工事現場で働く移民労働者自身であり、彼らが携帯電話やスマートフォンで撮影した動画に、アフメド・マータルがネット上で公開されている動画を掛け合わせたにすぎないという点である。
こうした雑多な映像作品は、従来の芸術概念からすると、あまり評価されにくいのかもしれない。稚拙で粗い映像には、いかなる意味でも審美的な価値を見出すことができないし、グローバリズムの時代における移民労働者という主題は含まれているにせよ、映像はあくまでも表面的な記録の羅列であり、主題を探究するという一面は特に見られないからだ。そもそもアフメド・マータルの名義で発表されているとはいえ、動画を編集しただけの作品はオリジナリティという点でも大いに疑わしい。しかし、この作品はヴァナキュラー映像として評価するべきである。
ヴァナキュラー(vernacular)とは、昨今建築や写真の領域で注目を集めている概念で、一般的には「地方のことば」、すなわち「方言」を指す。ヴァナキュラー建築とは、それぞれの土地の資材を用いながら風土に適合させた民俗的な建築であり、ヴァナキュラー写真とは、無名ないしは匿名の人々によって撮影・愛好される、いわゆる普通の写真である。従来の建築史は普遍的な建築様式を、従来の写真史は芸術性を、それぞれ重視したあまり、ヴァナキュラーを切り捨ててきたが、近年、既存の歴史が隘路に陥るにつれ、そのヴァナキュラーが見直されつつあるというわけだ。
むろんヴァナキュラーという論点が浮上した背景には、手頃な値段で入手できるカメラや動画機能をあらかじめ備えた携帯電話およびスマートフォンといったデバイスの技術革新と流通が挙げられる。だがより重要なのは、それに伴い、今日の写真がスナップ写真を、そして今日の映像が動画を、それぞれ内側に組み込むようになり、それまで鑑賞者という客体に過ぎなかった私たちが、時と場合によっては、撮影者という主体に容易に反転しうるという状況に変化したという事実である。このような構造的な変化を敏感に察知し、自らの作品に反映してみせたのが、アフメド・マータルにほかならない。
2015/03/31(火)(福住廉)
ジュピター
ウォシャウスキー姉弟による『ジュピター』は、ある意味で、あまりにも残念すぎて、スゴイかもしれない。実は人類が支配されている、現世では平凡な主人公が世界を救う英雄だったなど、中二病的な陰謀史観は、彼らの傑作『マトリックス』と一部共通しているが、全体としては最新の技術で大昔のSFを見ているようだ。映画美術として中世風の建築は食傷気味だが、フランク・O・ゲーリーの建築群をコラージュした都市風景は笑える。
2015/04/01(水)(五十嵐太郎)
暗殺教室
映画『暗殺教室』はあまり期待せずに鑑賞したら、十分に合格点の内容だった。漫画は最初の方しか読んでいないので、途中から原作との照合はできていないが、無理に完結させなかったのがいい。もともと漫画でも、絵的にリアリティのレベルが違う不条理な存在として、殺せんせーは登場していたので、よくできたCGの微妙な違和感がちょうどいい。また、二宮和也の声優ぶりもよかった。
2015/04/01(水)(五十嵐太郎)
古賀絵里子「一山」
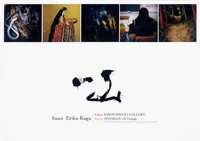
会期:2015/04/01~2015/04/10
エモン・フォトギャラリー[東京都]
古賀絵里子は2009年にはじめて高野山を訪れ、ほとんど啓示としかいいようのない「決定的」な衝撃を受ける。とりわけ、その奥の院は「六感にまで訴えかけてくるようで、その独特の雰囲気には圧倒された」という。翌月から、月一度ほどのペースで通い詰め、2010年の春からは山内に撮影の拠点となるアパートを借りた。だが自然の景観を中心に撮影していた写真には、3年ほどで行き詰まりを感じ、それからは高野山に暮らす人々にも、積極的にカメラを向けていくようになる。「「写真」以前に「人」がある」と考えたからだ。そうやって、少しずつ「一山(いっさん)」のシリーズが形をとっていった。
このシリーズは、既に2013年に、同じエモン・フォトギャラリーで個展の形で発表されたことがある。その後も着実に撮り続けて枚数を増やし、展覧会と同時に発売された写真集(赤々舎刊)の収録作品は、100点にまで膨らんだ。今回は、そのうち40点を選んで展示している。シリーズとしての骨格は、2年前の個展の時にでき上がっていて、それほど大きな変化はない。だが、単純に枚数が増えただけではなく、その間に結婚して京都に移り住むという大きな出来事を経験したこともあり、写真を選び、並べていく手つきに、揺るぎない確信と深みが加わったように感じる。1枚1枚の写真が伸び広がり、結びつき、照応し合ってあらわれてくる世界に、女性らしい細やかさを残しながらも、堂々とした風格が備わってきているのだ。タイトルの「一山」というのは、高野山の別名であるだけでなく「ある一つの山」という意味でもあるという。つまり、固有名詞である高野山に収束するだけではなく、より普遍的な、人と自然と宇宙との出会いの場をイメージして作品を作り続けているということだろう。そのことが、たしかな実感をともなって伝わってきた。
こうなると次作も楽しみになってくる。いい意味で期待を裏切って、新たな領域にもチャレンジしていってほしい。なお本展は、2015年4月18日~5月10日に、京都・妙満寺に会場を移して開催される。
2015/04/02(木)(飯沢耕太郎)
春を待ちながら──やがて色づく風景をもとめて

会期:2015/02/28~2015/04/05
十和田市現代美術館[青森県]
阿部幸子、高田安規子・政子、野村和弘によるグループ展。共通しているのは、いずれもささやかでひそやかな手わざによる作品という点である。
野村が発表したのは、おびただしい数のボタンを集積したインスタレーションなど。来場者が持ち寄ったボタンを投入させる観客参加型の作品である。高田姉妹の作品は、透明な吸盤に緻密な模様を彫り込んだり、軽石から円形競技場を彫り出したり、いずれも非常に繊細で緊張感の漂う制作過程を連想させる。ボタンや吸盤などの日用品を素材にしながら、ささやかでひそやかな感性を育んでいる点は、昨今の現代美術のひとつの傾向と言えるだろう。
とりわけ印象深かったのが、阿部幸子。会期中の毎日、会場内でパフォーマンス作品を披露した。白い雲が立ち込めたかのような幻想的な空間の中心で、阿部自身がはさみで紙を切り続けている。行為そのものは非常にシンプルだが、その白い雲が彼女が切り出した紙片の塊であることに気付かされると、その行為にかけた並々ならぬ執念と反復性に驚かされる。このような持続的な行為の反復は、数ミリ単位の細長い円形模様を長大なロール紙の上に繰り返し描きつけた彼女のドローイング作品にも通底していた。
はさみは紙の四辺に沿ってリズミカルに進む。その音はマイクで拾われ、会場内に大きく反響している。脳裏を刻まれているように錯覚する者もいれば、封印したはずの遠い記憶が呼び起こされる者もいる。視覚的には単純な情報しか入ってこないにもかかわらず、脳内では実に多様で豊かな感覚が生まれるのだ。
しかし思えば、このような変換による感覚の増幅こそ、美術の可能性の中心ではなかったか。本展で展示されていた作品は、華々しいスペクタクルを見せつけるようなものでも、コンセプトという知的ゲームに溺れるようものでもなく、ごくごく控えめで、どちらかと言えば地味な部類に入るが、いずれも美術の王道を行く作品であると言えるだろう。
2015/04/02(木)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)